適法な相続対策を知ろう
~相続税の節税方法の具体例~
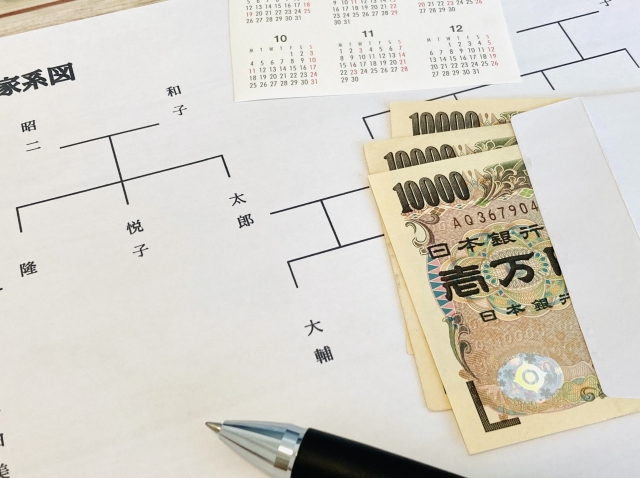
自分の死後、自宅などの不動産や預貯金などの財産の相続にあたり、相続税はどのくらいかかるのか心配な方が少なくないでしょう。
相続税はすべての相続においてかかるわけではありません。遺産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下である場合は、課税対象になりません。たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の場合は、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)以下なら相続税はかかりません。
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、だれしもなるべく支払う相続税を抑えたいと考えるでしょう。後々「マルサ」がやってくることがない、適法な相続対策の例を解説します。
①生命保険による相続対策
親が掛けていた死亡保険金の受取人が子などの法定相続人の場合、受け取る保険金は相続税の対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」に相当する額までは非課税です。
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の場合は、1,500万円(500万円×3人)以下なら相続税はかかりません。よって、死亡保険金額の総額が1,500万円未満なら、その額まで増やすことが考えられます。
また、相続開始時において保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額の評価方法の活用もできます。その価額は相続開始時において当該契約を解約する場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。
たとえば、被保険者を配偶者、受取人を子とし、契約者が死亡した場合、一時払い保険料1,000万円を現預金で支払ったとします。解約返戻金が800万円だった場合、200万円を遺産総額から減らすことができます。つまり、遺産総額から現預金1,000万円が減り、生命保険契約に関する権利800万円が増えるので、その差額です。
②養子縁組による相続対策
たとえば、孫1人を養子にすれば、法定相続人が1人増加します。それにより、遺産にかかる基礎控除額や死亡保険金にかかる非課税額を増やすことができます。
ただし、養子は被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人という上限があります。また、孫は被相続人の1親等の血族でないため相続税が2割加算されるというデメリットがあります。
③不動産による相続対策
たとえば、現預金1,000万円で土地を購入すると、土地は時価の80%程度で評価されるので、その差額分だけ節税することができます。
さらに、土地の評価は、その用途によって異なります。敷地上に貸家を建てたり、貸地としたりすることで、土地を自用とする場合に比べて評価額を下げることができます。
計算式は次の通りです。なお、借地権割合は国税庁が30~90%で定めており地域によって異なります。路線価図で調べることができます。借家権割合は一律30%です。賃貸割合とは、家屋全体に占める賃貸部分の床面積の割合です。
㋐貸家建付地(敷地上に貸家・賃貸アパートを建てる)
評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
㋑貸家・賃貸アパート
評価額=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
㋒貸宅地(第三者が建物を建てて使用することを目的として土地を貸す)
評価額=自用地評価額(1-借家権割合×賃貸割合)
ほかに、小規模宅地等の特例を活用できる場合もあります。
④生前贈与による相続対策
相続開始前に、つまり存命中に財産を贈与する方法もあります。贈与税の基礎控除額110万円を活用し、毎年この範囲内で贈与していく暦年贈与なら贈与税もかかりません。
ただし、相続開始前一定期間内に被相続人から財産を贈与された場合、その財産の贈与時の価額は、相続税の課税価額に加算されます。つまり、現行(2023年12月時点)では、相続開始時から遡って3年以内に贈与された財産には相続税がかかるのです。
また、相続時精算課税制度を選択した場合は異なります。特定贈与者(同制度にかかる贈与者)から相続や遺贈により財産を取得した財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。
なお、2024年以降、贈与税・相続税の改正により、変更される点があるので注意が必要です。

具体的な相続税や相続対策については、必要に応じて専門家である税理士のサポートを受けることになるでしょう。相続税の有無にかかわらず、自分の相続はいずれやってきますので、将来のために基礎的な知識は理解しておくことをおすすめします。

